半導体業界の最近のブログ記事
官民の半導体プロジェクトが消える
(2015年12月10日 20:23)1995年以来続いてきた、産官学共同プロジェクトのSTARC(株式会社半導体理工学研究センター)が来年3月に解散する予定にあり、最後というべきフォーラムが開かれた。惜しむ声は多いが、企業が必要としなくなりつつあったので、解散もやむを得ない。とはいえ、ネットワーキングの機会が失われることは指摘しておきたい。
半導体産業では、これまで何度となく国家プロジェクトが進められてきた。国家プロジェクトを進める「大義名分」は、日本の半導体産業の国際競争力を付けるためであった。結果は、余計悪くなっていった、である。はっきり言って全て失敗である。なぜ失敗と言えるか。日本の半導体産業の国際競争力が急速に失われていったからである。しかし、霞が関の官僚は「国家プロジェクトは成功だった」という結論を導いた。だから、なぜ失敗したか、という解析を全く行ってこなかった。名前は言えないが、複数の業界関係者は上記のように述べている。
半導体産業のエンジニアは製品に問題が起こり、市場で不良品とされた場合、日夜奮闘してその原因を探るため実験と測定を繰り返し解析する。そして不良の原因となった問題を明らかにすることにより、解決策を考察し実行してきた。この結果、不良品を二度と作らないようにする対策を講じてきた。このようにして良品率を上げ、より良い製品作りにまい進してきた。
ところが、官僚は失敗を「成功」と評価したため、問題を見つけることができず、その解析もせず、さらに解決案も提示できなかった。だから失敗を何度も繰り返してきたのである。国家プロジェクトである以上、税金を投入して官民を挙げて「先端技術」を開発し、その成果を見せてきた。しかし、こういった「成果」は半導体産業では使われない、使えないものばかりだった。国家プロジェクトに参加した企業は、「使えない技術」を企業に持ち帰っても、ガラクタにしかならなかった。
近年になると、優れた技術もいくつかは開発されてきた。しかし、時すでに遅し。企業、特に親会社側は研究所で開発された技術を正しく評価できないため、使わないという決定を安易に即決した。
そもそも、国際競争力をきちんと定義していなかったことにも問題があった。先端技術さえ開発すれば、世界に勝てると錯覚していた。しかし、世の中は、先端技術を必要としない市場が徐々に拡大してきた。いわばムーアの法則から外れる技術が増えてきたのである。半導体産業の大きな特長の一つは、半導体製品の他分野への浸透・拡大である。従来は、電子産業と言われる市場にしか製品を出していなかったが、半導体製品は機械産業、自動車・輸送産業、物流産業、医療機器、ヘルスケア産業、航空機、化学産業、農業、鉱業、通信、電力、ガス、エネルギーなどありとあらゆる産業に浸透し拡大してきた。
半導体製品の広がりは、必ずしも先端技術が求められるという訳ではなかった。加えて、ソフトウエアを半導体チップに組み込むことで差別化を図る手法も浸透してきたため、先端技術が全てではなくなってきたのである。にもかかわらず、国家プロジェクトは「ハードウエアの先端技術の開発」しかテーマに選ばなかった。米国のプロジェクトであるSEMATECHが2000年代に「低コスト技術」をテーマにして、安く作り利益を確保することに注力したのと対照的であった。例えば、インテルやTI、アナログデバイセズなどは、高付加価値の高集積ICを安く作ることに集中し、売り上げに対する営業利益率30~40%を獲得してきた。売り上げのシェア拡大は二の次であった。まずは利益を確保し、企業活動を継続させることが主眼にあった。対する大手日本企業は今でも10%未満の利益率が極めて多い。
日本企業が圧倒的な優位に立っていたDRAM製品でさえ、徐々に負けていったが、これはコンピュータの世界がダウンサイジングという大きなメガトレンドに沿って進んでいたのに、半導体は市場を見ずに技術を極めることしかやってこなかったからである。ダウンサイジングはなぜ起きたか。大型のメインフレームコンピュータやスーパーコンピュータは1台数億円~数十億円と高価であったために、いつでも誰でも使える訳ではなかった。フォートランなどでプログラムを書いて、コンピュータのプログラマに持って行ってもすぐには使えず、3日後に処理します、と言われた。いわば「待ち時間」が付きまとった。このため、コンピュータを使いたい人たちは、性能が少し落ちても1000万円程度で買えるオフコンやミニコンを欲しがった。これだと一つの事業部で1台持てたからだ。実際にコンピュータを動作させる時間は長く遅いが、次の日に結果が出れば帰宅時にスイッチを押して帰れば翌日には計算結果が得られる。性能が落ちても安いコンピュータの方が実質的に「速い」のである。だから、メインフレームよりもオフコンやミニコン、ワークステーションへと広がり、スーパーコンピュータも同様に、スパコンよりもミニスパコンが普及してきた。
半導体産業はダウンサイジングを知らなかった。みようともしなかった。もし、コンピュータが安価な方へと流れるメガトレンドを知っていたら、安く作るための設計技術・製造技術を開発すべきであることは明白だった。しかし、日本のDRAMメーカーは韓国企業が安いDRAM製品を出してきたときは見下してバカにし、人件費の高い米国のメーカー、マイクロン社が安いDRAM製品を出してきて初めて蜂の巣を突いたような大騒ぎになった。黒船到来のような騒ぎで「マイクロンショック」とも言われた。
もちろん、霞が関もダウンサイジングを知らなかった。先端技術を極めれば競争力は高まると錯覚していたのである。ただ、霞が関にとって国家プロジェクトは「天下り先の確保」でもあるため、企業がまとまれば支援する、という態度を取り続けた。今でもその姿勢は変わらない。逆に、半導体という言葉に対するアレルギーを持っており、責任もって業界を指導するという官僚が減っているという話がちらほら聞こえてくる。
では、国家は産業に対して何をすべきか。企業ではできない人脈形成のネットワーキングや企業に成り代わって産業を正しく評価できる「眼」、そして企業にアドバイスするコンサルティング機能などがありうる。その一つ、セミナーや講演などを通じてのネットワーク作りは、ビジネスを遂行する上で欠かせないプロセスだ。シリコンバレーやハイテク地区では大変重要なイベントである。半導体や部品メーカーがアップルやグーグルの人たちとそういった「場」で対等に話ができる機会がある。この場に参加できるかできないかは大きく違うだろう。世界的にもビジネスでは人脈が非常に重要な要素となる。現実に英国では政府の下部組織がセミナーを運営し、ネットワーキングを主催している(参考資料1)。日本ではメディアやセミナー業者が請け負っているが、赤字になることも多い。だからこそ、政府がネットワーキングに予算を採り、業界のつながりを広げていく支援を行えばビジネスに生かされるであろう。
(2015/12/10)
参考資料
三角関係の最新半導体企業買収劇
(2015年11月24日 22:27)今週、米国は感謝祭がある。毎年11月の第4木曜日に行われ、翌金曜日も休めば4連休となるため、今週の木金は静かになる。その連休前を狙ったのかどうかわからないが、半導体企業の買収が先週2件も立て続けにあった。さらに合併までいかないまでも、大型の提携も相次いだ。
まずオンセミコンダクター(ON Semiconductor)がフェアチャイルド(Fairchild Semiconductor)を買収することで合意したと発表した。18日にはタワージャズ(Tower Jazz Semiconductor)がテキサス州にあるマキシム(Maxim
Integrated)の8インチウェーハ処理工場を買うと発表した。
オンセミのフェアチャイルド買収は「トンビに油揚げ」の感がある。11月はじめに、欧州のSTマイクロエレクトロニクス(STMicroelectronics)がフェアチャイルドの値踏みをしていたという噂があった。ST以外にもオンセミとインフィニオン(Infineon Technologies)の名前も買い手の候補として挙がっていた。そして、11月19日にオンセミから突然の発表があった。オンセミはコンファレンスコール(ウェブによる電話会見)を開催、オンセミはフェアチャイルド買収によってパワー半導体でインフィニオンに続く第2位の地位を得ようとしたのである。
買い手のオンセミは、かつて世界第1位の半導体メーカーであったMotorolaから分離して生まれた企業である。MotorolaはマイクロプロセッサやマイコンなどのIC事業をフリースケール(Freescale Semiconductor)とオンセミに分けた。オンセミは当初ディスクリートトランジスタを中心に手掛けていたが、これだけでは他社と差別化できないため、IC化を進めるため小さいが専門的な企業を買収し続けてきた。三洋電機の半導体は安く買えたようだ。三洋側が手放したかったためだ。
一方のフェアチャイルドは名門企業だった。かつてムーアの法則のゴードン・ムーア氏とインテルの社長・会長を経験し故ロバート・ノイス氏らが設立した。「商用のシリコン半導体に集積されるトランジスタ数は毎年2倍で増えていく」という法則(後年になってムーアの法則と呼ばれるようになった)を学会誌に発表した時は、この二人がインテルを設立する前のフェアチャイルド時代だった。老舗と言ってよい企業である。集積化が遅れ、近年はパワー半導体に特化した企業で細々とやってきた。今回、最初から冷や飯組のようなオンセミがハイテクビジネスに成功して、かつての老舗を買収したのである。
マキシムを買収するという噂はこの最近出ていた。当初は、アナログデバイセズ(Analog
Devices)がマキシムを買うという噂があった。その後、TI(テキサスインスツルメンツ:Texas Instruments)がマキシムを買収するホワイトナイトだとも言われた。こういった買収劇は水面下で行われるため、噂しか伝わってこないが、先週の18日に入ってきた最新ニュースは、イスラエルに本社を持つタワージャズが8インチ工場を買うと発表した。

図 シリコンバレーにあるマキシム本社
これもトンビに油揚げかと思ったが、よく考えてみると、タワージャズは製造専門のファウンドリであるため、工場しか欲しくない。マキシムは200mmウェーハラインのアナログとミクストシグナル半導体メーカーで、その工場はタワージャズが手掛けるポートフォリオに一致しており、タワージャズが生産能力を上げるために必要な設備が揃っている。工場を拡張し、さらに世界中に拠点を広げるためには外国工場の買収が手っ取り早いといえる。
こういった買収劇は、基本的に自社の足りないところをカバーするために行う。かつての買収劇は相手をつぶすために行った。つまり、ライバルを買収した後、役員を全員追い出し、支配した。あるいはファンドが買う場合は、従業員のことなどお構いなしに、まるで商品のように工場や企業を売ったり買ったりして利ザヤを稼いでいた。映画「プリティウーマン」でリチャード・ギアが扮するM&Aのやり手の仕掛け人はまさに売ったり買ったりするだけのセールスマンだった。しかし、この映画の最後には、モノづくりを大切にして買った企業をそう簡単には売らないことを約束するようになった。
今の米国の買収劇は、ファンドでも相手をつぶす訳でもない。企業の活力は若い社員で決まり、彼らのやる気(モチベーション)を高めて、自発的に仕事をしてくれる会社が伸びることを米国の経営者は学んできた。だからこそ、社員の士気を高め、効率よく働いてもらうことを心がける。このため、簡単には首を切らない経営者も増えた。景気が回復し優秀な人を採用することが難しいことを知っているからだ。不況が来たら、あらゆる経費を見直し、コストを詰めて乗り切る。その代り、好況になりそうだと判断したら、積極的に投資する。こういった時期を経験すると社員のやる気は高まり、企業の業績も上がるという訳だ。
買収先の企業の得意な製品や技術を熟知していれば、買収によって自社の製品ポートフォリオが拡大し、顧客に対して幅広い製品を提案できるようになる。2010年にオンセミに買収された旧三洋電機半導体部門の人たちからは、かえってハッピーになったという声を聴く。同様に、スパンション(Spansion)に買収された富士通のエンジニアも、新技術を積極的に開発させてもらえるので、充実感に満たされていた。富士通にいた時は、半導体事業を縮小するのだから技術開発をやめろと言われたという。そのスパンションも、昨年サイプレス(Cypress Semiconductor)に買収された。しかも、買収を提案したサイプレスの日本法人社長には、元スパンションで営業を担当していた若いマネージャーが就任した。このような人事はこれまでになかった。
最近の企業買収は、無駄をそぎ、自社のない分野を手に入れ、製品やサービスのポートフォリオを広げ、より多くの顧客を獲得するための手段となってきた。もはや自社がゼロから開発する時代ではない。開発に数カ月かかるのなら、企業を買って技術を手に入れる方が結局安くつく。IoTをはじめインターネットやイントラネットを活用して、自社の生産性を上げたり工場の生産効率を上げたりする新しい変革の時代だから、M&Aが盛んになっているといえよう。
(2015/11/24)
半導体工場は既にIndustry4.0
(2015年11月12日 01:01)11月11日、半導体製造工場の歩留まり向上/生産性向上を目指すインテリジェントな仕組みであるAEC(Advanced Equipment Control)/APC(Advanced Process Control)Symposium 2015が東京一ツ橋の学術総合センターで開催された。これは、半導体製造工場内の製造設備にセンサを設け、そこからのデータを収集・解析しフィードフォワード的に製造条件を予測・設定することで歩留まりを高めようという自動化システムのことである。待てよ、これってIndustry 4.0のことではないか。

図1 AEC/APC Symposium 2015の風景
そう。実は国内の半導体工場はすでにIndustry4.0を適用している。東芝、ルネサスエレクトロニクス、パナソニック、三重富士通セミコンダクターなどの工場は、すでにIoT端末(センサ)を製造装置内に導入し、温度や圧力、プラズマパワー、プラズマ密度、ガス流量等さまざまな製造条件から半導体薄膜の膜厚や電気的特性など膨大なデータを解析している。これらのデータはビッグデータといえるほどの膨大であることも数年前から指摘されてきた。
数ヵ月前、ある半導体メーカーの北欧工場の方が日本で記者会見を開き、その席上でIndustry
4.0について解説した。Industry 1.0は第1次産業革命であり、スコットランドの技術者ジェームズ・ワットが発明した蒸気機関を用いて工場の生産性をそれまでの手工業から圧倒的に高めた。Industry 2.0、すなわち第2次産業革命は蒸気機関から電力に代えて生産性をさらに高めた。1970年代から始まったIndustry 3.0にあたる第3次産業革命は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)を使って機械をプログラムすることで効率の良い動かし方を可能にした。いわば工場のIT革命だった。
そして、現在のIndustry 4.0は、IoTやセンサ端末を用いてデータを集め、それをインターネットやイントラネットに載せ大型コンピュータで解析し、最適な条件にフィードバックすることで生産性を上げようとするコンセプトだ。従来のPLCだと、あらかじめ人間が製造条件をプログラムしておくだけの道具にすぎなかったが、Industry
4.0は人間を介さず、センサからのデータを自動的に解析し、それを自動的にフィードバックするもので、まさに自律的に工場を動かす。
こういった説明を受けると、半導体工場はIndustry 4.0を先行していた、といえる。世の中の製造工程の中で最も進んだシステムを半導体産業は工場に導入することで生産性を上げていたのである。生産の良品率を意味する『歩留まり』は95%以上だとか、不良品の発生を最小限にとどめて生産してきた。そういえば、他の産業従事者から「歩留まり95%なんて信じられない」という声を聞いたことがある。
半導体産業は、低コスト化の歴史でもある。ムーアの法則は半導体トランジスタを限りなく安くするための指針であった。1個のチップにトランジスタを集積する数が1年に2倍の割合で増えていく、という法則である。これは提唱したゴードン・ムーア氏が述べているように当初は、社会現象を法則として説明したものだが、のちに主導原理のように変わってしまった。Intelの最新のプロセッサは50億トランジスタを集積しており、仮にそれが2万円だとすると、トランジスタ1個の値段は0.000004円、すなわち0.0004銭にすぎない。ほとんどただ同然である。
このおかげで半導体チップは、コンピュータとテレビやラジオなどの民生機器に使われはじめ、その用途は拡大していく一途であり、その拡大のさまは今でも続いている。工業機器、医療機器、ヘルスケア、スマホ、携帯電話、ICレコーダ、クルマ、電車、飛行機、ロケット、ロボット、スポーツシューズ、歯ブラシに至るまで、実にさまざまな分野へと広がっていった。従来は民生と企業向け、あるいは産業向けと言われていたが、今は社会インフラ(電力やガス、水道、橋、トンネル、道路など)や社会システム(行政、教育など)など社会にも進出している。まさに万能のツールとなっている。拡大の勢いは止まらない。
半導体製品を安く作るために生産性を高める。そのカギが、AEC/APC、すなわちIndustry 4.0であった。
残念ながら、国内の半導体産業は世界の企業に負けた。安く作るための設計技術が後手に回り少量多品種製品を安く設計できなかったからだ。国内の顧客ごとに合わせてカスタマイズすれば利益が出るはずはなかった。半導体産業は、グローバル競争が最も激しい産業である。だからこそ、グローバル情報にアンテナを高くし、国内よりも海外の動向をしっかりと捉える必要がある。
Industry 4.0を推進している国内半導体工場はもっと自信を持ってよい。海外情報に対する貪欲さに加え、低コストの設計技術、プラットフォーム化やプログラム化、標準化を確立すれば世界と競争できる。私は、必ず復活できる日を信じている。
(2015/11/12)
中国によるマイクロン買収の真相
(2015年7月23日 23:28)先週、中国清華大学グループの紫光集団(Tsinghua Unigroup)が米国のマイクロンテクノロジーに対して、230億ドルの買収提案を行った。実は最近、中国企業が米国企業への買収活動が活発化している。中国では半導体産業を育成し、世界を牛耳るための基幹産業に育てたいとする狙いがある。日本のように半導体産業を手放そうとしている国は、世界の常識ではありえない。
中国資本による米国企業の買収はマイクロン騒ぎが初めてではない。紫光集団による買収騒ぎの少し前の6月末、米国のCypress Semiconductorが米国のメモリメーカーのISSIに対して買収提案をしていたが、中国のファンドコンソーシアム、UphillがISSIに対してCypressよりも高い値段で買収を提案した。ISSIの株主はUphillに売ることを決めた。まるで横取りとも言えるような行動であった。さらに4月30日にはやはり中国の投資コンソーシアム(Hua
Capital Management、Citic Capital Holdings、GoldStone Investmentなどのファンドを会員とする組織)がイメージセンサチップメーカー米OminiVisionを19億ドルで買収した。半導体企業ではないが、5月には米Hewlett-Packardがデータネットワーキング事業を紫光集団に23億ドルで売却している。
これほどまでも中国企業が外国の半導体企業を買収する背景には、昨年10月に中国政府のMIIT(Ministry of Industry and Information
Technology:日本の経済産業省に相当)が国家集積回路産業投資ファンドを設立したことがある。このファンドこそ、中国に半導体産業を拡大発展させるための資金となる。総額は2兆円とも言われる。この時以来、中国の買収活動が表面化してきた。中国は、半導体業界の優秀な人材を探しており、これから人材の引き抜きも表面化してくるだろう。
中国は世界の電子製品を製造する工場として君臨してきた。半導体を外国から購入し、EMS(製造専門の請負業者)がアップルのアイフォーンをはじめとする多くのスマートフォンを作ってきた。このため中国では半導体製品を外国から購入することが多く、中国製のチップは極めて少なかった。市場調査会社のIC Insightsが調査した中国の半導体市場は、需要が極めて高く、供給が追い付いていない。それどころか、ますます引き離されている(図1)。しかし、半導体チップが電子機器の性能を決めるため、自国で半導体チップを生産していなければ、大事な肝を外国が握ることになる。何としても自国の半導体チップを生産したい、と中国政府は考えた。

図1 中国における半導体需要は供給に追いつかなくなる 出典:IC Insights
ところが、半導体製造ビジネスはそう簡単ではない。金をかけて製造装置さえ揃えれば誰でもできるという訳ではない。優秀な技術者がいて、生産現場の人間が考える能力を持たなければ作れない。実は、2000年ごろ、半導体産業を起こそうと政府が呼びかけたことがあった。筆者はその時の中国を取材するため、SMICからGrace、HH-NEC、Motorola、ASMCなどさまざまな半導体メーカーを訪問した。半導体工場の建設ラッシュとも言うべき上海のプードン地区は半導体工場を建てるための広い敷地がずらりと並んでいた。しかし、世界と太刀打ちできるほどの実力を持ったファウンドリ(製造専門の請負業者)はSMICだけだった。そのSMICでさえ、リーマンショック前後に一時会社の存立の危機に面した。ましてはその他の企業は全く育たなかった。
インテルが大連に作った工場は成功しているように見えるが実態はわからない。また韓国のSK
Hynixの無錫工場では2013年9月に火災事故を起こし、数ヵ月もDRAM生産が遅れた。半導体製造は、大きな投資、製造装置のノウハウ、製造技術のノウハウ、優秀な開発技術者、優秀な生産技術者などが必要な総合産業だ。経験とノウハウは何物にも代えがたい。ところが、これまでの中国の市場開放後のビジネスでは、お手軽に金儲けをしたいという考えの人が多かった。中国内でも「拝金主義」と言われてきた。残業をいとわず懸命に働き続ける、というワークスタイルは、台湾や韓国のような市場経済社会にはあったが、共産中国にはなかった。だから半導体産業は簡単には育たなかった。
そこで今回、中国は外国企業の買収という手段を使ってきた。これが最近の動きである。外国企業を優秀な技術者ごと買収してしまえば、中国製の半導体チップは生産できる。
中国にとって幸運なことはインテルが協力的なことだ。インテルは紫光集団の株式の20%を2014年9月に15億ドルで取得している。紫光集団は中国のスマートフォン用アプリケーションプロセッサAPUのファブレスメーカーSpreadtrum社を買収している。つまり、インテルはSpreadtrumのプロセッサをスマホやIoT端末などに使う目的で紫光集団の株式を買ったのである。インテルにしてみれば、かつてアプリケーションプロセッサを持っていたMarvell Semiconductorを手放してしまったという「トラウマ」があり、意地でも買い戻すわけにはいかなかった。ちなみにインテルはAPUのことを決してアプリケーションプロセッサとは言わない。モバイルプロセッサという呼び名にこだわるのは、このトラウマがあるからだ。
マイクロンの買収は、できないだろうという観測が早くも流れている。これまでのISSIやOmniVisionほど小さな企業ではないからだ。マイクロンは、巨大なメモリメーカーであり、かつてのエルピーダメモリを傘下に収めている。しかも、1株当たり21ドルという買収案は安すぎるという声もある。5ヵ月前は1株32ドルあったからだ。この先は、米国にある外国投資委員会の判断を待つことになるが、おそらく難しいだろう。
マイクロン買収に米国がNGを出すなら、中国資本は、今度は日本へ触手を伸ばすにちがいない。今や経済産業省には「半導体担当」になりたくなくて逃げまわる官僚が多いと言われるほど、半導体アレルギーになっている。これまで半導体産業を支援するために経産省主導の国家プロジェクトはことごとく失敗したという歴史があるからだ。
しかし、簡単に日本企業を中国へ売却するようでは日本の未来はなくなる。政府が売却を許可するなら日本の復活どころか、絶望的になる。何としても半導体を手放してはならない。
アラン・チューリング博士の考えは生きている
(2015年5月29日 00:39)コンピュータは、メモリに命令とデータを蓄積し、それらを読み出して、「1番地のデータを5番地にコピーせよ」というような命令を実行することで、制御や演算を行う。メモリに格納する命令やデータをソフトウエアで書き換えるだけで、さまざまな制御や演算を行わせることができる。こういった汎用の演算器、すなわちコンピュータの概念を生み出したアラン・チューリング博士の生き様を描いた映画「イミテーションゲーム/エニグマと天才数学者の秘密」を見た。

図 アラン・チューリング博士が描いた抽象画 エジンバラ大学にて筆者撮影
実用的なコンピュータを作り上げたのはモークリーとエッカートだと言われているが、コンピュータのすごいところは計算が速いことではない。ソフトウエアを書き換えるだけで、いろいろな業務を行うことのできる汎用性だ。例えば、地球の軌道計算や無理数のπ(3.14159....という数字)の計算だけなら、ロジック回路だけで計算させる専用計算機の方が計算速度ははるかに高い。
天才、アラン・チューリングは、映画の中で「専用の暗号解読器を作るのではなく、プログラムを変えるだけでいろいろな計算ができるマシン(エニグマ)を作る」と言っていた。彼が生み出したフレキシブルなコンピュータの概念こそ、現在のデジタル機器の基礎になっている。ほとんどのデジタル機器は、CPUとメモリ(主にデータを出し入れするRAMと、命令を格納するROM)、その他外部へデータを入出力するI/Oインターフェース、独自の周辺回路、で出来ている。パソコンはもちろん、デジカメもスマホもテレビもプリンタもカーナビも、デジタル機器と言われるモノの基本は、このCPUとメモリ、周辺回路、I/Oインターフェースである。ここにソフトウエアを載せることで、違う機能を実現する。
ソフトウエアは、全てゼロから開発しなくても済むように、基本的なOS、ミドルウエア、アプリケーションという階層構成になっている。それぞれのソフトウエアをそれぞれの専門家が開発することで、ソフトウエアはつながっていく。例えば、ゲーム用のソフトウエア(アプリケーション)開発では、アプリだけを開発し、OSは出来合いのものを使う。
今の半導体産業・電子産業は、それぞれの回路をそれぞれの専門企業が担当している。だから全てを1社が開発する必要がない。CPUならインテルやアーム、ミップスなどの回路を購入し、メモリだとサムスンやマイクロンの製品が秋葉原で手に入る。インターフェースは共通化・標準化されているから、これも簡単に手に入る。ソフトウエアでさえもOSだとアンドロイドやマイクロソフトのウィンドウズなどを導入すればよい。
では、何を持ってデジカメやスマホなどの製品ができ、他社の製品と差別化できるのか。それこそがアプリケーションやミドルウエアであり、周辺回路である。つまり、ここに注力して、それ以外の部品や回路は市販のモノで済ませる。これが、良いものを安く、早く作るコツである。
以前、1000億円しかないスーパーコンピュータ市場で、1000億円もの国家予算をかけるスーパーコンピュータの国家プロジェクトは、全てゼロから開発しようとしていた (参考資料1)。だから、このやり方はおかしくないか、と問いかけた。国から予算をいただいて仕事している人たちだと思うが、ブログが炎上するほど非難を受けた。
しかし、同じスーパーコンピュータでも東京工業大学の「つばめ」は、「京」の1/10のコストで同様な性能を得ている。もちろん、ソフトウエアによって、それぞれ得意・不得意の計算があるから一概には言えないことは重々承知の上だ。東工大の方法は、CPUを外から買い、他の差別化すべき回路、ボトルネックとなっている部分だけにフォーカスして開発してきたからこそ、安いコストで高性能なスーパーコンピュータを実現できたのである。この手法こそが、世界の勝ち組企業が使っている手法に他ならない。日本の電子産業が没落したのは、何でもかんでも自前でやろうとしてきたからだ。
今でも日本製のOSやCPUを開発しようという時代錯誤の発言を未だに聞くことがある。もうOSやCPUは差別化できる部品ではない。そのようなところにこだわっていると世界から取り残されてしまう。だからこそ、何を開発して、何を開発すべきではないのかを明確にして、ハードあるいはソフトの開発に力を入れるべきだろう。
では、すでに「京」の渦中にいるエンジニアが世界にコスト的にも、Time-to-market的にも負けないスーパーコンピュータに仕上げるためにはどうすればよいか。これが、参考資料2で提案した、プラットフォームとしてのスーパーコンピュータである。下位展開できるように、まるで、「レゴブロック」のように簡単に取り外しできるような仕組みのシステムを作ればよい。いわゆる「専用」のスーパーコンピュータを作っても絶対にコスト競争力は付かない。「超汎用」のスーパーコンピュータを作ることこそ、コスト競争力が備わる開発手法、すなわちプラットフォーム戦略だと言える。
専用の計算機ではなく、汎用の計算機を作ろうと考えた、アラン・チューリング博士の考え方は、さまざまな少量多品種、さまざまな応用に適用できる手法である。日本がキラーアプリの開発、という考えに凝り固まっていては、いつまでたっても世界の勝ち組の仲間入りはできないだろう。どのような応用にも柔軟に対応できるモノ(プラットフォーム)を作ることが変化の激しい時代に生き残れる考え方だといえる。
参考資料
1.
世界と比べて常識はずれな1000億円という高額のスーパーコン補助金(2013/05/10)
2.
スーパーコンピュータの補助金1000億円をジャスティファイする方法(2013/06/18)
日本半導体が成長するために必要なこと
(2015年5月14日 23:45)先日、久しぶりに、デザインセンターを開設するという発表を聞いた。何年ぶりだろうか。欧州オーストリアをベースとする半導体メーカーams社が東京・品川にデザインセンターを開設、そのために必要な優秀な(talented)アナログ回路設計者を募集している。かつて日本の半導体メーカーは、ICチップを開発・設計するためのデザインセンターを各地に開いた。外資系半導体企業も東京や関西、名古屋にデザインセンターをよく開いた。

しかし、最近では、「半導体=落ち目の産業」、という図式が経済産業省や産業界にあるようだ。半導体産業の本質を理解していない人間ほど、この傾向が強く、我々メディアの記者も同様だ。日本の半導体が製造を手放していくのに反して、編集コンテンツを製造にこだわり続けた「電子ジャーナル誌」は3月末に廃刊した。
昨年、世界の半導体産業は10%成長したが、日本だけがマイナスだった。日本が世界の成長の足を引っ張らなかったなら、もっと高い11~12%くらい成長していた可能性がある。円安の影響は、ドルベースで外国企業と比べると低い数字になることを考慮すると、日本市場がたとえ横ばいでもマイナス成長となってしまう。
しかし、半導体産業の本質は、今や製造ではない。半導体チップにソフトウエアを組み込むことができるようになったこと、それによってシステムを半導体チップに組み込むことができるようになってきたことだ(参考資料1)。たとえ微細化技術が止まったとしても、ソフトウエアという人間の知恵を組み込むわけだから、その成長の可能性は無限にある。
外国の半導体がいまだに成長できているのは、チップに埋め込むソフトウエアの開発に力を入れ、そのソフトウエアを差別化技術(コアコンピタンス)にしているからだ。
日本の半導体産業は、得意だった製造技術を放棄し、ファブライト・ファブレスに向かってきた。その割にシステム設計できるエンジニアを養成してこなかったツケが不振を増長している。製造工場が必要なのは、大量生産が未だに強く求められるメモリ(NANDフラッシュやDRAM)とCMOSセンサくらいなもの。それぞれ東芝、マイクロン(旧エルピーダ)、ソニーが自前の工場を持っているのは、20世紀型の(ソフトウエアを必要としない)大量生産方式が必要な製品だからである。NANDフラッシュメモリとCMOSセンサはこれからも市場があるから大量生産が求められる。だから当分はしのげる。しかし、メモリもイメージセンサも十分足りるという時代が来ると、さあ大変になる。
韓国のサムスンは、NANDフラッシュもDRAMも大量生産しているメモリメーカーであるが、製造だけを請け負う「ファウンドリ」事業も持っている。ファウンドリ事業は自社のブランドを持たない、「黒子ビジネス」である。サムスンに続きインテルもファウンドリに力を入れ始めた。しかし、日本は得意な製造を捨て、ファウンドリビジネスに切り替えることができなかった。自社ブランドにこだわり続けたからだ。
一方の台湾は、昔から自社ブランドよりは「実」を取る企業文化がある。古くはパソコンの請負製造をエイサーやマイタック、エリートグループなどが請け負っていた。次に半導体ビジネスを始めた時、製造だけの請負というビジネスを選び、TSMCやUMCという世界的な企業を生み出した。かつてはパソコンのケーブルやコネクタを生産していた鴻海精密工業は今や、iPhoneの製造を請け負う企業として世界一になった。いずれも自社ブランドを持たない。エイサーは今でこそ自社ブランドのパソコンを持っているが、ブランドにこだわらない。この柔軟さが台湾を一大IT/エレクトロニクス製品の巨大基地にのし上げた。
では、製造を捨てたこれから日本のファブライト半導体が生きていくためにはどうすべきか。システムソリューションを提案できるような、ソフトウエアとハードウエアを理解できる能力を持つことである。外国のファブライト/ファブレスメーカーは、これができるから成長できているのである。
幸い、ルネサスは5月12日の決算報告会で、ルネサスはこれからシステムソリューションを提案できる会社に脱皮する、と作田久男CEOが語っていた。もう、石(シリコン)の時代ではない。システムソリューションを握る企業が勝つ時代だ、という認識を持っている。だから、元日本オラクルの社長であり、長年IBMで活躍された遠藤隆雄氏を次期CEOに推薦した、と述べた。クアルコムやメディアテック、ブロードコム、ザイリンクスなどの成長するファブレス企業と同じようにシステムソリューションを提案できる企業を目指すのである。日本の半導体企業でここまで言い切った経営トップはいない。非常に頼もしい。筆者は、「システムソリューションの提案には優秀な人材が欠かせない。どうやって確保するのか。その選択肢の一つに企業買収は視野に入れているのか」と質問すると、作田氏は「企業買収の可能性はある」と強く答えた。エレクトロニクス業界にいる外資系のエンジニアも私と同様なことを言う。ルネサスのエンジニアと話をしている彼は「最近のルネサスは変わった。日本の半導体の中で最も将来成長できる要素を持っている企業だと思う」と言っている。
アナログとミクストシグナル半導体を手掛けるamsが日本にデザインセンターを開いたのは、日本市場が自動車製造と、産業機器の製造の大きな市場があるからだ。これまでの日本の半導体がだめだったのは、日本の民生エレクトロニクス業界を相手にしてきたからだ。日本の民生が沈みゆくから半導体も引きずられたのである。今のソニーやシャープが好例だ。だから強い半導体メーカーは海外市場を見る。国内なら民生ではなく自動車と産業応用を見る。むしろ、民生なら外国市場を狙うべきなのだ。
世界をよく見て、日本をよく見て、自社の強みを伸ばし、顧客のシステムを理解し、世の中の動向(メガトレンド)をつかめば、日本の半導体は必ず復活する。30年以上も前にディスクリートのマイクロ波ダイオードを開発していた時、上司から「君たちはもう、半導体の勉強はやらなくていいから、システムの勉強をしろ」と言われた記憶が鮮明によみがえる。SoC(システムLSI)は今その時代に来ている。
参考資料
米企業に買収されて復活する日本半導体
(2015年1月 3日 22:00)明けましておめでとうございます。今年もご愛読、よろしくお願いします。
国内半導体産業は、ようやく復活する気配が見えてきた。エルピーダメモリ、ルネサスエレクトロニクス、旧三洋電機半導体、富士通セミコンダクターなど今年はさらに伸びそうだ。
2012年2月に会社更生法の適用を申請したエルピーダは、米マイクロンテクノロジーに買収され、復活した。マイクロンテクノロジーは2014年に16%増の成長を遂げた。この数字は、2013年にマイクロンとエルピーダを合算した数字よりも16%も伸びたという意味である。世界の半導体市場の伸びが9%程度だったから、エルピーダを合併したことで相乗効果があったと見るべきだろう。
ルネサスエレクトロニクスは、2013年にオムロンからCEOとして作田久男氏を招へいし、企業改革を実行させた。まずは売り上げ比べて多すぎる人員と工場削減によるCOO(Cost of ownership:いわゆる工場の運転稼働コスト)をカットし、固定費を減らした。そのリストラコストに数百億円を使った。それを見越して、親会社3社からの出資と顧客(自動車関連企業)、産業革新機構からの出資を仰いだ。中でも革新機構は2014年3月31日現在、同社への出資比率は69.15%と桁外れに高い。つまり政府系ファンドがルネサスを支配した。
ルネサスは、財政支援だけではなく、成長戦略も実行した。ルネサスの成長戦略は、これまでのメーカー視点による製品ごとの事業部から、アプリケーションごとの事業部へ変えたと同時に、成長分野にフォーカスした。具体的には、自動車ビジネスを主体とする事業部と、IoT(Internet of Things)などの工業用市場を対象とする汎用事業部に分けた。この結果、7四半期連続の利益を挙げた。
富士通はマイコンとアナログ部門を米スパンションに売却した。スパンションは、富士通が休止した、45nmや28nmなどの最先端技術の開発を明言している(参考資料1)。旧富士通セミコンダクターのエンジニアは、合併前は戦々恐々としていたが、スパンションが示した先端技術の開発はエンジニアにやる気を惹起させた。スパンションのジョン・キスパートCEOはインタビューの時は、日本法人のエンジニアをいつも「Excellent
tremendously」と表現している。日本人エンジニアの優秀さを常に評価する姿勢を見せていた。「企業は人なり」を実践しているのがキスパートCEO(写真)といえる。

三洋電機の半導体部門はオン・セミコンダクタに組み込まれた。パナソニックが買収しなかった三洋電機の半導体部門をオンセミが買収した。オンセミは、かつてモトローラから独立したディスクリート主体の半導体メーカーから出発した。同じモトローラから独立分離したフリースケールは、単価の大きなマイクロプロセッサやSoCなど差別化できる製品を持っていたため、売り上げはオンセミよりも大きかった。オンセミは、これにめげず、アナログにフォーカスしながらアナログの強い企業や企業内の部門を買収し続け成長してきた。三洋半導体はアナログの中でもパワーマネジメントやミクストシグナル製品に定評があった。
オンセミは旧三洋半導体部門をSSG(システムソリューショングループ)として、組み込み、さらに元々あったオンセミの日本法人と協力して相乗効果を上げている。FAE(フィールドアプリケーションエンジニア)や営業、デザインセンターとのコラボを通して、デザインインの件数は前年同期比2~3倍、新規製品提案金額は同5倍となり、新規案件獲得金額は同70%増と増えた。提案金額の伸びが大きいのは、旧三洋電機ではほとんど提案がなかったからだ。半導体ビジネスは今や、ソリューション提案できるところが勝ち組となるビジネスに変わっている。オンセミのやり方は世界の時流に乗っているといえる。旧三洋の新潟および群馬の工場は、オンセミ全体の製品も製造する社内ファウンドリとして使われている。
米国企業に買われたおかげで、旧三洋半導体部門の海外売上比率は、三洋時代の10%前後からわずか3年で50%を超えるようになった。これは、日本の顧客が海外進出したり、海外に販売したりする場合にでもオンセミの販売ネットワークを利用できるようになったためだ。
これらの例は、米国企業に買収されたことで、日本の半導体は復活し、業績を伸ばし始めている。日本だけでは生き残ることはできなかった。このことは、海外の半導体と比べ日本の半導体がいかに歪(いびつ)で、世界との競争に勝てる体質を構築できなかったことをよく表している。
日本の半導体が世界とは全く違い歪であることの一つに、親会社との従属関係がある。例えば東芝やパナソニックの半導体事業は今でも一事業部門である。また、富士通セミコンダクターは100%富士通の子会社だった。ルネサスは日立と三菱、NECとの3社による合弁会社であった。
これに対して、海外では電機メーカーから独立した半導体メーカーは子会社ではなく、自立した会社である。ドイツのシーメンスから独立したインフィニオンテクノロジーズも、フィリップスから独立したNXPセミコンダクターズも、ヒューレット-パッカード(正確には先にスピンオフしたアジレントテクノロジーズから独立)を源流とするアバゴも、親会社からの出資比率は最初から10%以下だった。どれも現在は共にゼロ%である。モトローラから独立したフリースケールやオンセミも親会社の出資はすでにない。
完全独立の海外の会社を取材すると、自分の責任で自由に経営できるという喜びを社員みんなが共有していた。企業としてのリスクは高まるが、自由度がそれに勝り、社員のモチベーションは非常に高い。
これに対して、日本の半導体メーカーの経営陣には、親会社にいつでも帰れるという甘えが生まれる。しかも日本企業特有の雰囲気として、子会社の経営陣は親会社の顔色ばかりうかがっていることが多い。これでは世界の競争に全く勝てない。霞が関も親会社も最初から排除する組織こそ、日本の半導体メーカー復活の第一歩になろう。
参考資料)
1.
買収されて良かった~日本企業では先端技術を開発させてもらえなかった
[速報]クアルコムが600人をレイオフ
(2014年12月12日 21:31)ファブレス半導体のトップメーカーであり、世界第3位の半導体メーカーでもある米クアルコム(Qualcomm)が600名のレイオフに踏み切るというニュースが流れた。米国で300名弱、海外で300名をレイオフするという。
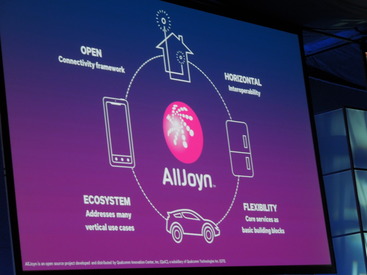
クアルコムは2014年の売り上げが11%増の191億ドル(2兆円強)を見込まれる優良企業である。世界の半導体産業全体が9%の伸びを示しそうだから、クアルコムの業績が決して悪い訳ではない。そのクアルコムがなぜレイオフに踏み切るのか?同社のスポークスパーソンは多くを語りたがらない。「定期的に自社ビジネスを見直しており、効率の良さを求め優先順位を付けている。社内のスキルやサイズを調整して、プロジェクトを辞めたり新規プロジェクトを開始あるいは伸ばしたりしている」と語るのにとどまっている。
しかし、これまでのクアルコムの動向を見ていると、理解できない訳ではない。クアルコムは3G通信のデジタル変調方式であるCDMAの基本特許を持っていた。3G通信は、ノキアやNTTドコモなどが使ってきたWCDMAと、クアルコム自身が使っていたCDMA 2000 1xという主として2方式が使われた。KDDIが採用していたCDMA2000は、クアルコムのチップを買うことで使えたが、WCDMA方式の携帯電話を作るとその特許料を携帯電話メーカーあるいは半導体メーカーが支払ってきた。クアルコムにとって3Gビジネスはどちらの方式でもお金が入る仕組みになっていた。
ただし、唯一の例外がメディアテック(MediaTek)だった。台湾のメディアテックは自社のチップが中国で偽物携帯電話機に流れてしまったことへの反省から、流通経路を見直し、偽物機メーカーが入手できないようなルートを確保することをクアルコムに約束し、ライセンス料を無料にしてもらったらしい。このため、メディアテックは、WCDMAモデムのライセンス料を支払わない分安く提供できた。これによって急成長を遂げた。
3Gモデムチップは、実はLTEになっても音声データのモデムに使われてきた。このためクアルコムはLTE時代でも繁栄できた。もちろん、クアルコムは、LTEに関する特許を持っている。しかし、同社以外の多くのモデムメーカーもLTE技術の特許を持ってはいる。このため、クアルコムにとって、LTEは基本特許ではないため、必ずIPRで稼げるという訳ではなくなった。しかもLTEでは、音声データもLTEネットワークを使うVoLTE(Voice over LTE:ボルテと発音)技術が普及するようになれば、音声用の3Gモデムチップは要らなくなる。
さらにクアルコムにとって、メディアテックという存在が大きくなりすぎた、という不運も重なってきた。メディアテックは売り上げがルネサスエレクトロニクスとほぼ並ぶ、第11位の企業に成長した。コスト競争力では、クアルコムはメディアテックにかなわない。中国市場ではメディアテックの方が強い。
LTE時代はクアルコムにとってマイナスの材料が並ぶ時代になってきたのである。だからこそ、スマホの急速充電規格である、Quick Charge 2.0や、クルマのワイヤレス給電技術に力を入れ、Wi-FiのIEEE802.11ac技術のアセロスと802.11adのウィロシティを買収した。11月にはBluetoothの老舗CSR社を買収提案するなど、ワイヤレス技術の全てを取ろうと必死である。
(2014/12/12)
「青色LEDは誰の発明か」議論が盛んな米国
(2014年10月27日 23:58)米国で電子技術者の学会組織であるIEEEのSpectrum誌や、半導体のウェブサイトSemiconductor Engineeringなどで、誰が本当に青色LEDを発明したのか、という議論が活発だ。2014年のノーベル物理学賞に3名の日本人が受賞したことに対して、この3名がふさわしいのかどうかの議論もある。
IEEE Spectrumのウェブ版では、「青色LEDの特許は実に多い」、「ノーベル・ショッカー:RCAは1972年に最初の青色LEDを光らせた」、「LEDの父はノーベル賞を受賞しない」などの話が詰まっている。Semiconductor
Engineeringでは、「誰が真の青色LEDの発明者か?」というストーリーを掲載している。
青色LEDがノーベル賞のテーマになる2年も前の2012年に、米国カリフォルニア州のシリコンバレーの街の一つ、マウンテンビューにある「コンピュータ歴史博物館(Computer History Museum)」において、ダグラス・フェアベイーン氏がメンターグラフィックス社CEO兼社長のウォリー・ラインズ氏にインタビューしている物語が記録されている。ラインズ氏の生い立ちからエンジニア、そして経営者になるまでのインタビューだ。
この中に、修士課程のスタンフォード大学の研究室で、RCAからPh.Dを取得するためスタンフォード大学に来ていたハーブ・マルスカ氏と一緒に机を並べてラインズ氏は研究していたことが述べられている。ラインズ氏はGaAsを、マルスカ氏はGaNをLEDの材料として選んだ。マルスカ氏はまだ誰も手掛けていなかったMg(マグネシウム)ドープのGaN結晶を作った。p型の半絶縁性GaN結晶に電極を付けたMIS構造ダイオードで青色の光を放ったという(図1)。そして1974年に特許を取得した。学生時代はn型GaNを作れなかったため、pn接合にはなっていなかったとラインズ氏はそのインタビューに答えている。しかし、マルスカ氏はRCAでn型のZnドープのGaNの作製に成功し、p型はできなかったと述べている。
図1 1972年RCAでハーブ・マルスカ氏が試作した青色LED
最初に青色LEDを発明したのは、ハーブ・マルスカ氏であることは間違いないようだ。しかし、同氏は今回受賞しなかった。マルスカ氏にとって、青色LEDを実用化できなかったことの方が悔しいようだ。RCAは社長のデビッド・サーノフ氏が死去した後、息子が後を継いだものの、コンピュータ事業に手を出し、失敗に終わり経営がガタガタになった。そして1974年に青色LEDのプロジェクトは解散させられた。
マルスカ氏は赤崎勇氏にも会っており、彼が1990年にあるホテルの部屋にいた時、ノックする人がいたが、それが赤崎氏だったという。赤崎氏は青く光るLEDをマルスカ氏に見せ、マルスカ氏は興奮したと述べている。
赤崎氏がいつからGaNを手掛けたのかははっきりしないが、Wikipediaには1986年に低温堆積緩衝層技術による高品質GaN結晶の作製に成功とある。当時の青色LEDあるいはレーザーの開発にはZnSeかGaNか、という競争をしていた。1989年にpn接合のGaNの製作に成功、青色LEDを実現した。中村修二氏は赤崎氏とは別にGaN結晶成長を手掛けていたが、1993年に高輝度の青色LEDを開発したとWikipediaには述べられている。中村修二氏は日亜化学工業の社長に3億円もの開発費を認めてもらい、青色LEDの実用化に成功したと言われている。
そのマルスカ氏は3名のノーベル物理学賞受賞のニュースを聞いて、次のように述べている。「3名の受賞者は本当に称賛に値します。私はよく言うのですが、蒸気機関の開発に携わってきた人たちは何人もいます。しかし、ジェームズ・ワットが実際に動く機械を作るまでは誰も実現できませんでした。ノーベル賞に値する人は本当に動くものを作った人たちに与えられるべきだと思います。受賞者3名は称賛に値します」。
マルスカ氏のこのコメントは大人の言葉である。自分が最初に青色LEDを光らせたのだから、ノーベル賞は自分がもらうはずだ、とは決して言わない。
しかし、赤崎勇氏と天野浩氏のグループは、中村修二氏とは互いの仕事について決してコメントも引用もしないようだ。文部科学省傘下のJSTが制作したビデオ、「青色発光ダイオード開発物語~赤崎勇 その人と仕事~」を見て、中村氏の名前が決して出てこないことは異常である。青色LEDの実用化に大きな寄与を果たした一人が中村修二氏に違いないことに疑問の余地はない。しかし、このビデオには一言も出てこない。赤崎氏と中村氏が犬猿の仲であることは業界では公知の事実だ。だが、マルスカ氏の大人の態度と比べると、日本のノーベル賞受賞者は大人になり切れていないと思ってしまう。こう思うのは私だけだろうか。
(2014/10/28)
ユーザーエクスペリエンスが重要な時代を生きる方法
(2014年7月21日 13:55)半導体を中心に、その応用であるモノづくりやITなどのシステムを見ていると、半導体陣営とITや産業機器関係者との将来の見方に温度差を強く感じる。ざっくり言えば、半導体関係者は悲観的、IT関係者は楽観的だ。ITでは、2020年には500億台のマシンやデバイスがインターネットとつながる時代になり、データレートはギガビットからテラビット単位に高速になるというような明るい未来を描く。半導体エンジニアは現在最先端の20nmプロセスの先には14/16nmプロセス、さらに10nm、7nmまでくると、もう限界ではないかとささやいている。
この温度差は何か。半導体エンジニアはハードウエアのことしか考えていないからではないだろうか。半導体だけしか知らない者は、原子レベルと微細化を比較し、微細化のレベルがそろそろ原子レベルに到達していくことを知っている。量子論的な不確定性原理やトンネル効果、電子の波としての性質などが見えてくる。だから限界がくる、とすぐに結論付けるのであるが、もっと目を開けて応用面を見てほしい。
AMDが28nmプロセスの新型プロセッサ(図1)を発表していた時に、記者から「インテルの22nmプロセスのHaswellと比べて、28nmプロセスでは性能が見劣りするのではないか」という質問が出た。その問いに対してAMDは「今のプロセッサは性能を争う時代ではありません。ユーザーエクスペリエンスが競争力になっています。このアプリケーションプロセッサに集積しているGPUとCPUをうまく使えば、これまでにないユーザーエクスペリエンスを提供できます」と答えた。つまり時代は、性能から、ユーザーエクスペリエンスつまりユーザーが楽しいと驚く体験を提供できるかどうかにカギがある方向に動いている。だからこそ、半導体の限界を追求することも重要な技術の一つだが、それが全てではないのである。

図1 AMDのアプリケーションプロセッサ「Bald Eagle」
こういった兆候は数年前から見られた。2009年の電子情報通信学会のMEMS研究会で招待講演の機会をいただいたときにお話させていただいたが、その時はユーザーエクスペリエンスという言葉がなかったために、MEMSを使って楽しさを表現するデバイスがこれからも伸びると述べた。iPhoneと任天堂のWiiが登場していた。どちらもMEMSセンサを使って楽しさを表現していた。MEMSセンサがこの頃から急速に伸びていく。
この講演で、MEMSチップはセンサ部分とCMOS信号処理回路を無理に集積しなくてもコストが見合う方法でやるべきだと述べたら、大学の先生からお叱りを受けた。「僕らはCMOSとMEMSの集積化を研究しているのに」と言われた。研究は進めれば良いのだが、生産性や歩留まりが悪くてコストを安くできないのであれば最初から使われない。低コスト化には設計段階からの関与が必要だからである。
ただ、低コストでしかも楽しさを表現できるデバイスにMEMS技術が数多く使われている。スマートフォンやタブレットには3軸加速度センサや3軸ジャイロセンサ、3軸磁気センサなどMEMS技術を使った機能が多い。ただし、MEMS研究者・開発者はとかくMEMSセンサ部分しか見ないことが多い。重要なことはMEMSの出力信号を楽しさに変換して表現するためのアルゴリズムの開発とセットだということ。このためにはアルゴリズム開発者と手を組んで共同開発することを考えなければ、売れるような商品にはなりえない。アルゴリズムと商品開発からコストに見合う技術を選ぶのである。エコシステムはここでもとても重要になる。
CMOS半導体を見ると、製品に使われる最先端プロセスは20nm。MOSFETのゲート長、ゲート幅を20nmとすると、チャンネル内表面には、20nm×20nmの面積しかない。この面積内に電子を発生させるドナー不純物がいくつあるか、数えてみよう。シリコン結晶は1立方cm当たり10の24乗個あるとして、ドナーは5×10の17乗個で電流をオンさせると考えると、20nm×20nm×5nm(チャンネル深さ)の体積は2×10の-18乗であるため、この中にドナー不純物は1個しか含まれない。つまり、1個あるかないかという数字が出てくる。ゲートしきい電圧Vthは不純物濃度ともろに関係するから、Vthは不純物の有無で大きく揺らいでしまうことになる。つまり、現在でもすでにMOSトランジスタの動作限界に近づいているのである。それでも半導体エンジニアは、ドナー不純物の影響をチャンネル領域で受けない構造を提案するなど、技術は進む。
一方、性能がかなりのレベルにまで上がってくると、半導体チップの競争は機能で勝負することになる。機能の中でもユーザーエクスペリエンスが最も重要な要素になってきたのがここ最近のこと。だからこそ、半導体を使ったシステム開発者やサービス提供者は、半導体の機能に期待する。機能には限界がない。
もう一つ、半導体エンジニアの認識が低いことに、半導体にソフトウエアをインプリメントできるという意識が薄いこと。ソフトウエアで機能やユーザーエクスペリエンスを表現できれば、価値ある半導体チップになる。だからこそ、微細化を進めて限界を極める必然性が薄れてきているのである。
では、半導体エンジニアがとるべき道は何か。機能を実現する手法を応用面からユーザーと共同で開発することに尽きる。だからこそ、ユーザーと、ソフトウエアからハードウエア、特にデジタルだけではなく、アナログ技術も含めてディスカッションでき、ユーザーが数年後に望むチップをイメージする能力が求められる。半導体エンジニアにとって、半導体の勉強よりもシステムの勉強の方が重要な時代に来たといえる。
(2014/7/21)


