メディア業界の最近のブログ記事
私はなぜグローバル企業を取材するか
(2019年4月 6日 12:22)日本企業がグローバル化あるいは国際化を声に出して言うようになったのは、わずか10年くらいしか経っていない。2002年まで在籍していた日経BP社(入社したときは日経マグロウヒル(McGraw-Hill))時代に、日本がグローバル市場で勝つためのアイデアをブログ(記者の眼)に書いたとき、「何でグローバル化が必要なのか、本当に取材したのか」といったコメントをいただいた。つまり読者はグローバル化を全く意識していなかった。その後、2008年にセミコンポータルでセミナー「グローバル化をどう進めるか」を開催したときも、なぜ今、このテーマでセミナーを開くのか、という声も聞いた。
今から10年ほど前までは、グローバル化という言葉はほとんどなく、海外進出、という言葉が新聞などのマスメディアを飾っていた。私は、1992年から2002年までNikkei Electronics Asiaという英文雑誌を担当しており、アジアへの取材、アジアの企業の眼で日本を見るという仕事をしていた。韓国、台湾、香港、シンガポール、さらにマレーシア、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム、インド、オーストラリア、中国を含めたアジア太平洋の地域・国を読者対象としていた雑誌である。
現地と付き合わなかった日本企業
当時、多くの日本企業がこれらの国や地域に進出し、日本のプレゼンスを上げていたのだろう、と勝手に想像していた。ところが現地のエレクトロニクス企業に取材してみると、日本企業をほとんど知らない。付き合いもない、ということだった。唯一、韓国のサムスンは日本の半導体製造装置を導入していたため、日本とはなじみがあったが、韓国内のLGや現代は日本との付き合いも日本企業もほとんど知らなかった。ましてやマレーシアやインドネシア、中国の地元企業は日本企業についてほとんど知らなかった。
日本企業はずいぶんアジアへ進出していたのに、一体なぜか?エレクトロニクス企業だけを取材していた私は長い間疑問に思っていた。オーストラリアからの帰国便で隣に居合わせた東京銀行の方と話をしていて、ようやく疑問が解けた。日本の銀行がなぜアジアへ行くのか。日本の大手企業がアジアに工場を立てて操業するとなると、部品や部材などのサプライチェーンが構築できなければ工場を稼働させられない。このため、1次下請け、2次下請けも一緒に現地で工場を立てた。そこで働く日本からの従業員も数十名から数百名に上るようになると、日本の銀行も必要になる。大手企業の海外進出とは、海外で単なる「日本村」を作っていただけにすぎなかった。だから、地元企業との付き合いはほとんどなかった。
アジア向けの雑誌を担当する前は、日本語のエレクトロニクス雑誌を担当し、米国を中心に取材・出張することが多かった。1980年代当時のコンピュータや半導体、通信などテクノロジーは、未熟だったため、IEDM(国際電子デバイス会議)やISSCC(国際半導体回路会議)などのIEEE学会会議の取材が多かった。この当時、私の英語は未熟だったが、学会発表では分厚い丁寧な論文が掲載されており、英語を話せなくても論文から記事を書くことができた。ところが、学会資料だけでは米国企業の本音がわからない。米国企業を取材して、しっかりした考えを伝えるために、私も英語の会話を国内で勉強した。
今だからわかったことも
2002年に日経BP社を離れ、リード・ビジネス・インフォメーション(旧カーナーズパブリッシング)に入社し、日本のエンジニア向け新雑誌を発行するために、かつてのDRAMエンジニアに取材して話を聞いた時のことだ。彼は「ミスリードしない雑誌を作ってくれ」という注文をつけた。かつて日経BP社で「メモリからASICの時代へ」という特集記事を出したが、これがミスリードした、というのである。「日本は結局メモリに強い企業が多かったのに、こんな記事を経営者が読み、DRAMを放棄した」、と彼は続けた。だから日本の半導体がダメになった。
この話には二つの教訓がある。一つは自分が納得できない疑問が残り、彼とは論争になった。商業誌の記事で経営者が意思決定するのか、という疑問であり、そんなはずはない、と私は反論した。今になってみると彼は正しかった。事実、日本の電機経営者の多くは経営判断能力に欠けていた。当時若かった私は、電機の経営者を「立派なえらい人たち」、とみていた。もう一つの教訓は、当時の特集には間違いを含んでいた、ことである。海外取材をたくさん重ねるうちに気がついたことであるが、「メモリからASICへ」という流れは、米国だけだったのである。それを世界的なトレンドとみて、米国のトレンドはいずれ日本にも来ると見ていたが、これが間違いだった。米国の半導体業界では、多くの企業がDRAMで日本に負けたから自分たちを見つめ直して、自分の得意なところを探した結果、メモリ以外の半導体を追求するようになったのだ。
図 リードで発行していたEDN Japan別冊では国内外企業のトップを取材、新発見が多かった
自分の間違いの元は、米国企業を取材せず、単なる学会発表だけを取材していたことにあった。だから海外企業の本音を聞こうと努めるようになった。今になってからわかった事実もある。1980年代後半の日米半導体戦争の時のこと。米国は日本に対して「外国製半導体の日本市場シェアを20%に上げよ」という市場経済に反するような要求をしてきた。この要求を日本の霞が関は丸呑みした。ところが1~2年前、「まさか、日本がこの無茶な要求を丸呑みするとは思わなかった」という声を米国で聞いた。通常、交渉事では、最初に20%と吹っ掛けておき、他方は10%と主張し、最終的に15%くらいで手を打つのが本来の交渉である。このようにならなかったということは、霞が関の役人には交渉能力が全くないことが暴露されたといえる。
トレンドをフォローするグローバル企業
米国企業をきちんと取材していれば、日本の経営にも役に立つ事実が多くあることがわかる。それらをこれまでNews & Chipsなり、セミコンポータルなりで伝えてきた。しかし、日本企業の経営者がそれを参考にしたという形跡はない。ただ、ありがたいことに外資系企業の国内の経営者からは多くのコメントをいただいているので、読まれているようだ。最近、日本の研究者から、ある米国企業が立ち直った戦略を知りたい、という声があり、ボランティアで対処している。
海外企業の取材で最も面白いことは、この先のトレンドを常にフォローしていることだ。かつての日本はトレンドを見てこなかったために、井の中の蛙、あるいはガラパゴス、という状態に陥った。海外企業のトップも将来に向けたトレンドは、企業の将来を左右するため極めて敏感である。逆に、トレンドに鈍感な経営者は企業の命が危ない、ということになる。
(2019/04/06)
日立の意図とは違う新聞の見出し
(2019年1月31日 11:21) 1月25日、日立製作所は「風力発電システム事業の強化について」と題したニュースリリースを発表した。ところが、同日夕方の日本経済新聞は、「日立、風力発電機の生産撤退」という見出しの記事を報じた。これを見て、「あれっ?」と思わず叫んでしまった。全く否定的に捉えていたからだ。なぜ、こうなるのか。
実は、日経の見出しに間違いはない。かといって、日立が風力発電システム事業を強化することも間違いではない。しかし、見出しをパッと見て一つはポジティブ、もう一つはネガティブに見える。つまり、視点が全く違うということである。だから全く違う見出しに見えてしまうのだ。
事実はこういうことだ。日立は今後、風力発電機そのもののハードウエア部品を生産せず、これはドイツのEnercon社の発電機を使う。そして日立はIoTと同社のプラットフォームであるLumadaを駆使し、発電機から産み出させるたくさんのデータをコアとするビジネスに変えることを宣言した。発電機にはIoTは多数取り付け、そこからのデータを取得する。発電機そのものはグローバルな競争になり、メジャーなプレイヤーに絞られてきたようだ。このため、トップを取るために努力するより、発電機が生み出す膨大なデータを利用して顧客の価値を提供するビジネスに変えるのである。ハードウエアの生産からは撤退するが、今後期待が大きいデータビジネスには積極的に参加していくことになる。
図 ドイツの高速道路沿いにある風力発電の風車(本文とは直接関係ない) 津田建二撮影
風力発電機そのもののビジネスでは、高さが200メートルを超える超巨大なモノに変わりつつあるため、投資も時間も増えてくる。日立はハード部品での競争を止め、データサービスで稼ぐ方向にビジネスの中心を切り替える。だから「風力発電システム事業を強化する」とした。また、風力発電機が他のビジネス同様、シェア1位か2位でないと競争できないような体力勝負となれば、もはや日本の総合電機の出番ではない、と日立は判断したのであろう。風力発電機というハードウエアに資金も人材もかけるよりは、データビジネスに投資する方がさまざまな分野へも応用がきくからだ。
だからといって、新聞が生産撤退という見出しを付けるのはどうか?少なくともIT系に強い日経新聞はモノづくりよりもIT系やデータを重視しているはずではなかったか。データは未来の石油ともいわれており、先端的な米国企業は、データビジネスへの転換を急ぎ、デジタルトランスフォーメーションをリードする方向に向かっている。日立もデータは石油なりの方向へ舵を切り替えている。このように捉えても良かったのではないだろうか。
英国への原子力エネルギーの輸出に関してもコスト的に合わないと日立は見積もっている。これまで日本国内で原子力事業をやってきて、原子力はエネルギーコストが安い、と風潮されてきたが、リスクコストを全く見てこなかったからだ。3.11の福島原子力発電所の爆発とそれに伴う放射能汚染などのリスクを配慮すれば原子力のコストは決して安くない。石油や再生可能エネルギーではリスクコストはそれほど考慮しなくても済むが、原子力は万が一のリスクを配慮したコスト計算を含めることは世界の常識である。リスクは政府に見てもらう、といった態度では世界に輸出できないことを英国政府から教訓として学んだのである。日本政府のようにリスクは政府が面倒見てくれる、といった甘い態度は世界では通用しない。だから、ハードウエアでコストがかかりすぎるマシンからは撤退する、と決めた。
風力発電ビジネスでは、コストのかかるハードウエアを回避して、データビジネスで稼ごうと日立は力点を変えたのだ。この点を新聞は理解しようとせず、ネガティブなイメージで風力発電機の生産から撤退、という見出しを付けた。むしろ、日立がデータビジネスへのシフトにより、未来へ切り開こうとしている努力を垣間見ることができると思う。
(2019/01/31)
スマホの次は、やはりスマホ
(2018年2月15日 11:16)相変わらず、ポストスマホという言葉がメディアに載っている。スマホートフォンの次のデバイスを期待しようとしている。しかし、少なくとも今後5年くらいは、スマホの次はスマホである。なぜか。スマホは、いつでもどこでも座らなくても使えるコンピュータだからだ。コンピュータはマシンが同じでもソフトウエアを変えるだけでいろいろなマシンに変身できるというもの。これからのIoT時代では、IoTからクラウドに吸い上げたデータを可視化して、スマホやタブレッド、ファブレット(5~7インチのスマホ)でみることから始まる。IoTのその次は、解析したデータを完全自動でIoTへフィードバックし、スマホやタブレット確認しなくても自律的に改良する。これは5~10年先の話だ。
スマホはリモコンに
当分はスマホで確認する。先日、日立製作所の家電事業会社、日立アプライアンス社は、ロボット掃除機など家電製品をスマホで操作できるようにしていくと発表した。もはや専用リモコンは要らなくなる。リモコンの代わりにスマホで操作するようになる。家電メーカーはリモコンを作らなくて済むが、その代わりスマホで家電を操作するためのアプリを開発する。
スマホはそう簡単にはなくならない。これこそ、ユビキタスなコンピュータだからである。10数年も前にいつでもどこでもインターネットを経由して世界中を結ぶことができるユビキタス時代が来ると言われながら、どこかへ行っちゃった、と思っていることだろう。実は、スマホがユビキタスなデバイスだ。パソコンだと、いつでもどこでもつながっても椅子に座らなければ操作できなかった。スマホは、立ったままでも歩きながらでも操作できる。歩きスマホが迷惑問題になる時代だ。これがユビキタスである。
スマホは世界中とつながり、YouTubeを使えば自分の好きな時代の音楽や映画をいつでもどこでも楽しめる。ポール・マッカートニーやイーグルズ、ビージーズのライブを見ることができる。ABBAの音楽と「マンマ・ミーア」を同時に楽しめる。ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの「ミスター・タンバリンマン」や「時代は変わる」、といった音楽も聴ける。ベトナム戦争時に真昼の空から大量に落ちてくる爆弾を雨に例えて表現したと言われたCCR(Credence Clearwater Revival )の「Have you ever seen the rain?(雨を見たかい?)」は、悲惨なベトナム戦争のフィルムを背景にした音楽が流れ、胸が詰まる。CCRのボーカルでリードギターを務めたジョン・フォガティが、ブルース・スプリングスティーンとの共演ライブで「Oh! Pretty Woman」をハモると、悲惨な時代を乗り越えて生きてきたと感じる。
昨年はメモリの高騰でスマホも高騰しただけ
話は横道にズレたが、1月に開かれたCESの主催者CTAが発表した2018年の主要デバイスの成長率を見ると、ウェアラブルデバイスはもはや1%の伸びしか期待できない。GartnerやTrendForceなどの市場調査会社は2018年のスマートフォンを5~6%成長すると予測する。2017年のスマホはほとんど成長せず横ばいだったが、これは2017年にメモリ価格が高すぎたためにデバイスも高くなりすぎて、スマホは売れなくなったからだ。18年はメモリ価格が正常に戻れば、スマホも適正価格に戻り再び成長曲線に乗る。
スマホは、これから家電のリモコンになり、外出先からスマホを通して家のエアコンのスイッチを入れ、玄関のドアの鍵を確認できるようにもなる。その分、セキュリティがしっかりすることは言うまでもない。スマホが玄関の鍵となることさえありうる。アプリさえインストールすれば、使えるようにできるからだ。非接触カードのNFCは、スマホを入れてセキュリティも確保すると、決済機能を入れられる。フリーマーケットなどでクレジットカードの決済もできるようになり高価なカードリーダーは要らなくなる。スマホの応用はとどまるところを知らない。
スマホはまさに超汎用コンピュータであり、アプリケーションソフトを入れ替えれば何にでも化ける。ロボットやVR/ARもスマホと連動して動く。当然AIが入り込むし、クラウドを使ったAIはすでにSiriとして機能している。クルマとの連動も時間の問題だ。今や、通話機能は「ついで」になったケータイであるからこそ、スマホの次はなかなか登場しにくい。
(2018/02/15)
科学と技術は大きく違う
(2017年3月28日 00:34) 「地下の汚染水は、科学的には汲み上げてろ過して排水すれば安全」と言った科学者の発言がマスコミに伝わると「地下水は安全」という言葉に変わってしまう。科学的にはたとえその通りでも、技術的には初期コストや運転コスト、ハードとソフトの規模、安全かどうかの検証、など技術的に可能であることは全く何も実証されていないのである。このことは、科学者が「原子力は安全」と言う言葉と全く同じである。
科学的に可能であることと技術的に可能であることは全く違うのだ。技術は、コストまで含めた現実のソリューションを導けるかどうかを実証することまで責任を持つ。先ほどの科学者の言葉を、技術的に検討するために必要な技術的課題は多い。地下水を汲み上げるポンプはどの程度の容量が必要で、どこに設置できる大きさなのか、その初期コストや運転コスト(電気代)、ろ過するフィルタの交換頻度やろ過できる能力、ろ過し排水できるスループット(1時間あたりの処理量)、フィルタの設置場所や交換しやすさ、など、そしてろ過した後の安全性の実証も必要だ。たとえ初期的には安全でも時間が経っても本当に安全か、経時変化はないかどうか、ポンプを汲み上げる配管の劣化はないか、信頼性に問題はないか、などなど。技術的に安全だという根拠はゼロに等しい。
自動運転車でも科学的には可能だが、技術的にはまだ可能にはならない。技術的には、子供の急な飛び出しに対応できるか、白線の無いけもの道を走れるか、初めて通る道を走れるか、信号は認識でき、時速80km制限を読めるとしても、「飲んだら飲むな」という自動運転車にとって重要ではない標識にどう対応するか、などなど。自動運転に向けて取り組まなければならない技術的な問題は山積している。とても安全で今すぐ走れるという訳ではない。
矢沢永吉さんの「やっちゃえ、日産」という宣伝広告での自動運転は、車線を変更せず、しかも運転手は手を放してもすぐにハンドルを握れる状態にいることが、手を放してもよいと許される条件だ。つまり自動運転車でさえ、技術的にまだまだ課題は多いのである。
マスコミの「地下水は安全」という言葉は、それを信じる人たちにとっては、政治的に利用する言葉だったり、全く何も知らずに安全だと信じ込む人たちだったりする。言葉だけが独り歩きしてしまうことが最も怖い。これが風評につながるからだ。
科学者を責めるつもりはないが、言葉は勝手に独り歩きしてしまうことに注意してほしい。科学的にOKだ、という言葉は、できそうだ、あるいはできるかもしれない、という程度に見るべきである。技術はコストも含む。技術的に可能でも誰も買えない価格の製品だと、社会的には無意味である。ましてや科学は、原理だけで判断するため、科学者の言葉を即現実に持ってくることはおそらく間違いだろう。
アインシュタインの一般相対性原理は、重力場は光も曲げてしまう、というアイデアを含んでいるが、そのアイデアの証明は数十年も経ってからようやく最近あったばかりだ。重力場のアイデアを昔学生時代に知ったとき、本当かなあ、とまずは疑った。技術が発展し、やっと今頃になって実証できる環境が整い、ようやく証明できた。科学的には納得できることと納得できないことがある。ましてや、それが実証されていないことなら、すぐに信じてはいけない。
(2017/03/28)
心新たにiPhone誕生10周年
(2017年2月24日 01:16)シリコンバレーで新しいアップルの本社ビルの工事を見てiPhoneのすごさをつくづく感じる。2017年は、iPhone が誕生して10周年、そのハードウエアのカギを握る半導体トランジスタが誕生して70周年に当たる。iPhoneを最初に見たときは、大きなショックを受けた。2本指でピンチイン、ピンチアウトすると縮小・拡大を表してくれる。ところが、ある主要エレクトロニクス雑誌は、新しい技術が何もない、と切り捨てた。70年前も、トランジスタ開発の最初の記事は小さなベタ記事としてしか扱われなかったようである。
もちろん、その雑誌の記者は(私もそうだったからこそ自戒を込めて書いているが)、対象とする読者には常に取材して意見を聞いているため、記者というより読者である日本のエンジニアが、そう言ったのだろう、と推察する。iPhoneは、のちにアンドロイドのヒントとなり、新しい場を作り出した。iPhoneはある意味、世紀の大発明の一つに挙げられる。にもかかわらず、そのイノベーションのすごさを日本のエンジニアは理解できなかったといえる。
これまで、エンジニアの世界ではテクノロジーは、高性能・低消費電力が主な技術度の指数であった。その意味ではiPhoneに採用された高性能・低消費電力という指数からみると、すごいというものではなかった。しかし、iPhoneを最初に見た時、楽しそうな携帯電話だ、と直感した。指でページをめくる操作や、拡大・縮小の操作が親しみのある動作だったからだ。画面を90度左右に倒すと画面も一緒に見る向きに対応してくれる。人間になじみにある、こういった動作で表現する、「ユーザーエクスペリエンス」という言葉は、iPhoneから生まれた。
2007年に米国で最初に発表され、日本での登場には数ヵ月かかった。日本で導入される前に英国人から見せてもらった時の興奮は忘れられない。それまでの、いわゆるガラケーには、私は魅力を全く感じなくなっていた。だからiPhoneを初めて見たときは感激した。実は2000年ごろ、英国のベンチャーからテキストの拡大・縮小を実現するソフトウエアを見たときは応答が遅く、2~3秒かかったため、面白いとは思ったが、まだ使われないだろうと見ていた。2007年のiPhoneにその機能が入っていたのだ。しかもピンチイン、ピンチオフというわかりやすい動作で表現した。
iPhoneが発表してまもなく、GoogleはAndroidと名付けたOS(カーネルはLinuxで、厳密にはOSではなくプラットフォームというべきソフト)を発表した。しかも無料で提供すると発表した。翌年2月のMobile World Congress 2008では、テキサスインスツルメンツ(TI)が早くも、Android開発ツールボードを出展しており、その取り組みの速さに驚いた。日本のメーカーはこの時よりも半年以上、遅れた。
その後、Androidフォンが登場し、iPhoneやその前にビジネスパーソンに使われていたBlackberryを総称して、「スマートフォン」という言葉が生まれた。Androidの登場と日本メーカーの遅れは、そのまま現在の遅れにつながっている。
メガトレンドに鈍かった日本
ここで言いたいことは、時代の変化点を見つけるという意識が日本企業はあまりにも遅い、ということだ。このため、世界の動きについていけなかった。これが日本の最大の問題である。DRAMビジネスを韓国やマイクロンに負けた最大の原因は、経営者もエンジニアもみんなメガトレンドを見ずに来たことだ、この時代の「ダウンサイジング」というITの大きなトレンドを。
世界の動きは非常に速い。米国でも欧州でもアジアでもグローバルな開発競争が始まっていた2002年ごろ、日経BP社に在籍していた時、アジアや米国など海外を1000人以上も取材してきて、日本を何とかグローバル競争で勝つためには、少しでも日本が有利な条件で早くから戦うことだと思い、「外国企業の積極的な誘致が国内の活性化につながる」というブログ記事を書いた。この記事に対して、本当に取材したのか、グローバル化の必要性がわからない、といった声を聞いた。意識がとても低かったのである。日本にいて日本しか見なければ、本当にガラパゴス化してしまう。このことに対する危機感は今でもある。
iPhoneを見て、何も新しい技術はないと断じた失敗はもう許されない。新しい動きに対するアンテナ感度を少しでも高く上げてほしい。それもグローバルな動きに敏感に感じてほしい。新しいイノベーションは、日本だけではない。広く世界にアンテナを立てていなければ入ってこない。
実は筆者も大失敗した経験がある。日経エレクトロニクスにいた頃だ。1980年代前半に「半導体はメモリからASICへ」という趣旨の特集をやった。これは米国の姉妹誌Electronicsが企画した特集の翻訳だった。米国のISSCCやIEDMなどの学会IEEEを毎年取材していたのにもかかわらず、企業を取材していなかったために、技術の方向を示す実態を把握できていなかった。メモリからASICあるいは非メモリへ、という動きは実は米国だけの動向だった。米国の半導体メーカーは、DRAMで日本にやられたから、ロジックや非メモリへ進もうという動きだったのである。それを半導体産業全体の動向として、メモリから非メモリへという特集を発行した。のちにあるエンジニアから叱られた。「その特集を見て経営者がメモリをやめたのだから、君たちはミスリードした」と。
情報へのアンテナを高くせよ
メモリは今でも、日本が得意な製造に価値のある製品である。DRAMでマイクロンやサムスンに負けた原因をきちんと分析せず、DRAMをやめてロジックへ、システムLSIへと日本の半導体企業がみな舵を切った。この後の日本は惨敗の連続だ。たまたま他のメモリとしてフラッシュメモリを持っていることに気がついた東芝は、NANDフラッシュで大成功を収めた。ただし、戦略的に深く考察して、NANDフラッシュを選んだわけではなかった。舛岡富士雄氏(現在、東北大学名誉教授)が開発したフラッシュメモリをたまたま持っていたからそれを選んだだけにすぎなかった。
今、海外企業を取材するのは、私自身がミスリードを二度と犯したくないからであり、日本企業にもガラパゴスになってほしくないからだ。日本企業と海外企業を取材していると、その違いがはっきり見える。海外企業は常に新しい動向にアンテナを立てて探している。10万円もするセミナーに参加して動向を知ることにも投資を惜しまない。だからこそ、海外企業の成功例を紹介し、そのビジネス戦略の裏にあるものは何か、どのような考えで戦略の結論を出したのか、など参考にしていただきたいとの強い想いで、日本企業に向けた記事を作っている。
(2017/02/24)
キュレーションはジャーナリズムに立脚しているか
(2016年12月 9日 22:57)キュレーションメディア事業部を巡るトラブルで、DeNAの南場智子会長をはじめ首脳陣が謝罪会見を行った。weblioによると、キュレーション(Curation)とは、人手で情報やコンテンツを収集・整理し、それによって新たな価値や意味を付与して共有することである、という。英語のサイトを見ると(参考資料1、2)、キュレーションという言葉より、コンテンツキュレーションという言葉の方が多く散逸する。その基本は、様々なメディアからニュースをつまみ食いして、意味を付加することではない。様々な断片的なコンテンツから、新しい考え方を生み出すことで、ブレーンストーミング作業と似ているともいう。ジャーナリズムの本質を知らない「素人」が机の上で意味を追加すると「ねつ造」になりかねない。
さまざまな情報源から、断片的な情報をとってきて(すなわち取材し)それを整理し、ある視点から見ると新しいニュースやコンセプトに見えることがある。これがニュースの切り口とか、新しい視点という考え方である。
ところが、問題となっているキュレーションメディアは、インターネットから様々なコンテンツをつまみ食いして、勝手に別の意味を付け足しているから、「ねつ造」していたのである。実際に現場に行って取材して、ネットコンテンツの真意を確認していないのなら、そのような「ねつ造」はジャーナリズムとは大きく異なる。単なる「流布」や「噂」に過ぎない。こういった「ねつ造」が独り歩きした「流布」が出回ると多くの人たちが迷惑をこうむることになる。
従来は、井戸端会議で勝手な噂を作り出し、流してもそれほど広くは伝わらなかった。しかし、インターネットは「拡散」や「コピペ」などで他人が勝手にほかのホームページに張りつけることで日本中に広く拡散させることができる。出所を明らかにしても、事実ではない「流布」や「噂」を勝手にもっともらしく追加してあたかも独自記事のように見せかけるから、質(たち)が悪い。
いろいろなメディアからニュースを寄せ集めるだけのキュレーションならまだ許せる。ニュースピックアップは昔から、ニュースクリップとして何が起きているかを断片的ながら事実を集めて読むことができた。たくさんのニュース情報から見えてくるものを探ることはできなくても、事実だけを拾うことには価値があった。
さまざまなニュースから独自の視点でモノを書くとはどういうことか。独自記事を生み出す(創造する)ことは大変な作業である。だからこそ、著作権が発生する。さまざまな裏付け、資料、取材などを通して事実を整理し、まるでデータサイエンティストのように、起きている断片的な事実の根底に流れるトレンドを見出す。しかも見出したらそれを取材によって検証するのである。この作業ができるのは、ジャーナリズムを知り尽くした人間でなければできない。素人ができることではない。
おそらくキュレーションメディアと称する媒体はジャーナリズムの本質を知らないのであろう。だったらそのようなまねごとをすべきではない。キュレーションメディアの経営者は少なくともジャーナリズムを勉強してほしい。あくまでも事実をもとにコンテンツを作るという基本を勉強してほしい。ジャーナリズムには本来、「ねつ造」や「でっち上げ」、「うそ」があってはならない。事実は事実以外の何物でもない。その中から、ある視点で見ると全く新しい切り口が見えてくることがある。これがまとめ記事のタイトルとなる。
本来、コンテンツキュレーションは、社会問題を考察し論文にまとめて発表することと似ている。ここに「うそ」や「ねつ造」があっては、意味がないだけではなく、人々の判断を迷わせることになり、社会に悪影響を及ぼすことになる。事実を集めるだけではなく、裏付けをとり、事実だけで表現できないのであれば、コンテンツキュレーションというビジネスを行うべきではない。「うそ」や「でっち上げ」は、決して許される行為ではない。
参考資料
1. 17 of the Best Content Curation Tools to Use in 2015 (2015/04/06)
2.
How to Curate Killer Content
Ideas (2015/02/05)
(2016/12/09)
とと姉ちゃんに見るジャーナリズムの原点
(2016年9月21日 22:57) 10月1日に最終回を迎える朝の連続ドラマ「とと姉ちゃん」は、雑誌「暮らしの手帳」出版の社長であった大橋鎭子さんをモデルにした物語である。暮らしの手帳は、名物編集長の花森安治氏との名コンビで発行されていた。一般家庭のどこにでもあり、暮らしの役に立つ雑誌だった。
一方で、暮らしの手帳は、広告を入れずに購読料だけで運営していた。とても素晴らしい。雑誌ビジネスでは広告を入れることが常識で、その中で中立性をどのように保つか、ということにいつも腐心している。日経マグロウヒル(現在の日経BP社)は、B2Bのビジネス雑誌を扱う出版社であり、そのノウハウは米国のマグロウヒル社からきていた。ジャーナリズムの中立性は時には広告と相反することがある。この場合、編集者は結局、ジャーナリズムを理解していただく以外になかった。それだけに暮らしの手帳は、ジャーナリズムの原点ともいえる中立性を厳しくこだわっていた。私が参加していた当時の日経エレクトロニクスの島津和雄編集長(故人)は、日経新聞出身者で、暮らしの手帳を褒めていて、あのような雑誌ができないものかと、いつも思案されていたことを思い出す。
ドラマの場面でも出てきたが、暮らしの手帳は洗濯機などの電化製品のテストを社内の実験室で行っていた。広告を入れると中立性を保つことが難しいからだ、とその姿勢を貫いた。エレクトロニクスでは、雑誌社が半導体や部品のテストをすることは極めて難しい。オシロスコープやスペクトルアナライザ、信号源、DMM、ネットワークアナライザなど測定器を買いそろえ、かつトランジスタなどのDUT(被試験デバイス)に印加する電圧レギュレータもそろえる必要があり、とても一つの雑誌社で賄えるものではなかった。測定器は今や100万円単位のものから精度が高ければ1000万円を下らない。雑誌社が商品テストを行うには無理があった。
それでも中立・公正な記事を提供することは、ジャーナリストとしての基本である。昔は、商品カタログに札束が入っていたことがあったと聞いた。日経マグロウヒル時代、ある企業から5000円のオレンジカードという一種の商品券がカタログの裏に入っていたことがあった。資料を受け取ったときは気が付かず、そのまま社に持ち帰ったが、さすがにそれは返却した。しかし、その企業からは二度と新製品情報が来なくなった。
どこからも圧力を受けずに記事を貫きたいと思っても、エレクトロニクス・半導体の世界では、書いた記事を発行する前に見せてほしい、という要求を受けることがある。しかし、これはお断りする。検閲に相当するからだ。スポンサーなり取材先なり、意図したことがたとえ違っているとしても、それはそのメディアの捉え方であり、実力でもある。それについて干渉されるのであれば取材しなければよい。
ただし、自分で書き間違えたと気付いた場合は訂正する。要は、事実とは違う場合には訂正を出すが、取材の相手が語ったことが事実ではなかった場合には訂正ではなく、「申し出」という形で記事を修正する。ワシントンポストやニューヨークタイムズのような海外媒体でも同じである。訂正に相当する「Correction」と、申し出に相当する「Clarification」とははっきり区別する。
どのような場合でも書いた記事を事前に見せろという注文には応じないのであるが、エレクトロニクス業界では、このような要求は絶えない。それでも辛抱強く、理解してもらう努力は続ける。近いうちにまた英国に取材に行くためのアポを取ったが、事前に記事を見せてもらえるかどうかを聞いてきた。それは丁寧にお断りし理解を求めた。結局、取材を受けてくれた。
ジャーナリズムの原点は、起きている事実を伝えることである。かつては意見を載せてはいけないと言われた。インターネットが身近になるまでは、報道に徹した。読者は、記者の意見など聞きたくもない、と思っていたからだ。事実を事実として淡々と伝えることが重要である。それが良いか悪いかは読者が判断することだから。ジャーナリズムは伝えること、報道することが主要な仕事であった。
しかし、取材しているうちに、インターネットで誰でも情報を発信でき、情報が溢れる時代になると、逆に「あなたの意見を述べてほしい」と言われるようになった。○○社がXXを開発した、という新製品・新技術情報ならニュースリリースや他の媒体で手に入るからだ。ジャーナリストの故筑紫哲也氏は、TBSのニュース番組でキャスターとして事実を伝えるだけの仕事と、自分の意見を述べる「多事争論」を区別していた。
インターネット時代には、企業側はニュースリリースだけではなく、ブログという手段で情報を流す。海外媒体のブログは、日本のブログとは全く違い、何を食べたなどの情報は一切流さない。あたかも中立性を装うかのような記事風のストーリーで事実を述べている。だからこそ、ジャーナリスト側も様々な角度から事件を取材、検証し、正しい真実の姿を追求していく。ある角度から見ると、ニュース価値のある視点が生まれるときは、何かを発見したかのようにうれしくなる。「暮らしの手帳」ほどの中立性は保てないだろうが、できるだけそれに近づける努力はしていかなければならない。
広告を出す側の人たちと話をしても彼らもメディアには中立性を求める。自分の企業に都合の良い記事はむしろ歓迎されない。他の企業に対しても同じことをしているのだろうという疑念を持たせてしまうからだ。現実に広告と記事を混同させて没落した雑誌やメディアは数えきれないほどある。だからこそ、中立性を保ち、かつ「評価」を加えることが事実を読みやすい物語として伝えることになる。
数多くの取材をしていれば、評価としての意見を求められることが多いが、ジャーナリストの基礎となるものは豊富な取材である。勝手な思いこみは真実から見ると害になる。思い込みが事実と違っていれば、こちらが事実に合わせて新しい視点を見出さなければならない。この発見こそ、ジャーナリズムの神髄である。誘導質問などもってのほか。事実からますます離れてしまうからだ。とと姉ちゃんのドラマの中で、商品の公開試験を取材したことにより、暮らしの手帳の本質に迫った新聞記者がいたが、それはジャーナリストの好例といえる。
(2016/09/21)
メディア買収による編集の独立は?
(2016年6月19日 09:28)最近、米国のエレクトロニクスメディアのEE TimesおよびEDNを持つ出版社UBMを電子部品商社(代理店)のアローエレクトロニクス(Arrow Electronics)が買収するというニュースが流れた。EE Times、EDN、いずれも日本版を持っているが、日本版の発行元はUBMとは全く関係がない。ITメディアというウェブメディア出版社が両方の日本版を持ち、翻訳権を買っている。
かつて、EDN Japanという雑誌に係わったことがあるが、この発行元のリードビジネスインフォメーション(旧カーナーズ)の米国の編集グループと編集上の問題をディスカッションした。米国の広告営業グループとも付き合わせてもらった。特に米国リードが持つ雑誌を3誌(Electronic
Business、Semiconductor International、Design News)の日本版、創刊を手掛けた関係上、米国の編集者だけではなく広告の発行人ともずいぶんディスカッションさせてもらった。広告営業の発行人は、対象読者を絞り、広告を求めている読者層かどうかの検討を何度もやり取りした。米国と欧州、中国、アジア、日本、と電話会議もよくやった。
B2Bの雑誌では対象読者が見え、彼らに広告の製品を買ってもらいたい企業は、漠然とした読者像を嫌う。読者が広告掲載製品を買える責任があるかどうか、かなり具体的な製品まで要求される。アメリカ流の購買層訴求のステップはシステマチックに進められることが多い。ただ、そうはいっても最後はやはり人間関係が決め手となる。だからといって、接待漬けにすればよいというものではない。個人差が大きく、接待を嫌う人も中にはいる。ただ、やはり決め手となるのは人間性である。嘘をつかない、常に立場をわきまえてくれる、顧客の立場でソリューションを提案してくれる。口下手でもかまわない。朴訥(ぼくとつ)でも誠意があって正直であれば、顧客は安心してくれビジネスになる。むしろ、口八丁手八丁の営業スタイルは嫌われる。
インターネットの時代になると、日本だけではなく、米国のB2Bメディアも紙からネットへの転換を迫られるようになった。紙は広告効果が見えないため、出稿する側はより効果が見えるメディアや手法を求めるようになった。良質な読者が読んでいて評価しているかどうかの確認を欲しがった。最近はバナー広告のページリクエストもGoogle Analyticsではなく自分でカウントしたがる企業が増えてきた。
今回は、アローという電子部品の商社がメディアを手に入れた。メディアの編集者の中立性は保たれるのであろうか。メディアは広告をもらうから記事を書くとか、広告主や読者層に遠慮してずばり切り込まないのなら、メディアの価値は必ず下がる。歴史は語っている。アローはどのようにEETやEDNを扱うのだろうか。
かつて日本でも、チップワンストップというオンライン電子商社がEE Times Japanという雑誌を発行したことがある。チップワンストップはまさにアローの競争相手である。しかし、2~3年しか続かなかった。インプレスに売却、その後はITメディアに移った。現在はITメディアが発行しており、それなりの地位を確立している。特にEE Times米国が発行している特ダネ記事を即日翻訳掲載しているが、ここに面白いコンテンツが多い。
チップワンストップはなぜEETJを手放したのか。詳細は不明だが、当時のEETJでは、ほかのメディア同様、他社の広告を入れていた。しかしチップワンストップ以外の広告が入りにくかったということだろう。逆に言えば、発行人が一般のメディア並みの広告を要求したのだと想像できる。しかし、これは無理な話だ。出版業として独立していないメディアを1つの業界企業が持てば、その企業の宣伝媒体と思うのが自然だからである。編集人は、編集記事の独立性は保たれている、と述べていたが、一般企業の広告担当者から見れば独立性が保たれていようがいまいが、1企業が発行する媒体である以上、同じ業界にいる別の会社としては広告を出したくない。そのような媒体に出すつもりなら他の媒体に出す方が有効だと思うにちがいない。シングルスポンサーの雑誌であり、他社からの広告は期待できないメディアだと発行者が割り切れば、続いたと思うが、残念ながらチップワンストップ側がこのことを理解できなかったのだろうと想像する。
シングルスポンサーのメディアは実は最近出てきている。WirelessWire Newsがそれだ。広告主は表面には出ず、ウェブ上は編集コンテンツのみだが、経費を抑える編集スタイルでメディアとして存続している。もちろん、記事の中立性は担保されている。
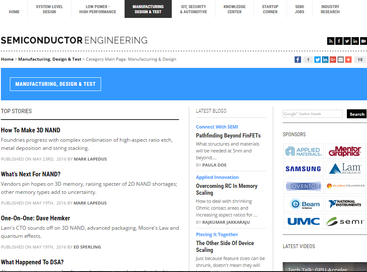
図 Ed. Sperling氏が発行する固定スポンサー方式のメディア
米国でも、元リードでElectronics Newsの編集長をしていたEd. Sperling氏が立ち上げたSemiconductor
Engineeringがシングルではないが、複数スポンサーのメディアとして運営している。これは半導体専門のウェブサイトだが、システムレベル設計、低消費電力・高性能、製造・設計・テスト、IoT・セキュリティ・自動車、ナレッジセンター(ホワイトペーパー)などのコラムを作り、コラムごとのページにスポンサーを入れている。
今回、アローがEETとEDNを買収して、電子商社の広告塔的なメディアであり、他の企業からの製品広告は期待しないのであれば、うまくいく可能性がある。そのためには収入がないのであるから、編集コストを削減しなければならない。編集の質をどれだけ重要に思い、独立性にどれだけこだわれるか、すべてアロー側がメディアをどれだけ理解しているかによる。アローに都合のよい記事を編集者に要求するなら、編集者はみな去っていく。
メディアの価値は中立・独立性にある。米国の編集者は中立性へのこだわりは日本の編集者よりも強い。やはりジャーナリズム先進国だけある。日本では、記事を事前にチェックさせてくれ、記事を訂正してくれ、というような要求が企業側からよく来る。しかし100%ミスでない限り訂正はしない。記事の表現や企業のニュアンスが入っていないことで、訂正を要求するところもあるが、これは検閲行為になる。記事が出る前の事前チェックも検閲である。数字を書き間違えたというような明らかなミス以外、編集者は訂正しない。そのための編集の基本ルールは、中立・公平かどうか、である。もちろん編集側のでっち上げや、やらせは、問題外である。
(2016/06/19)
坂本氏の新メモリ会社の会見を中止させたもの
(2016年3月 6日 22:03)2月24日午後1時から久々の先端メモリ開発会社発足の記者会見が開かれるはずだった。会社名はサイノキングテクノロジージャパン株式会社。会社の代表者であるCEO(最高経営責任者)は、かつてエルピーダメモリを指揮してきた坂本幸雄氏である。しかし、残念ながら会見はお流れになった。なぜか。

会見開催の知らせが来たのは、2月19日(金)の19:14のメールだった。この第1報では、開催日時が13:00となっていたが、プログラムには13:30から挨拶から始まるという、不整合な案内だった。このあと22日(月)の10:53に、開催日時13:00、開始も13:00挨拶、という整合性のとれた会見訂正の案内が入った。
記者会見の案内では、「この度、日本・台湾の技術力と中国の資本力を基に、先端メモリの開発を行う新しいプロジェクトをスタートする運びとなりました。つきましては、下記のとおり記者会見を催したいと存じます」とあった。差出人は「サイノキングテクノロジージャパン㈱ CEO 坂本幸雄」である。
同時にその22日の日本経済新聞朝刊に坂本氏が新しいメモリ会社を設立するというすっぱ抜きのニュースが載ったのである。どのメディアも、記者会見の案内を受け取ると、24日まで待って、その設立の趣旨や狙い、見通し、背景、進行状況などについて話を聞くだろう。その会見をきちんと待っていた。にもかかわらず、日経はその前に記事を載せた。しかも、記事内容があやふやでちっともわからない。「日台と中国を中心に設計や生産技術の担当者を採用して、1000人規模の技術者集団を形成する。(中略) サイノ側が次世代メモリを設計し、生産技術を供与する。第1弾として、(中略) IoT分野に欠かせない小電力DRAMを設計し、早ければ17年後半に量産する」と報じている。
日本と台湾がDRAMの設計会社で、中国の製造会社に技術を供与して作らせるということなのか。中国では最先端技術は輸出できないため、どうやって製造装置を揃えるのか。次世代メモリとは何なのか。第1弾としてIoT向けの小電力DRAMとあるが、IoTセンサ端末向けなら外付けDRAMは要らない。マイコンに内蔵のRAMで十分。またIoT端末は省電力がマストだが、演算能力は要らない。電池を数年間メンテナンスフリーで使う用途が多いからだ。ただし、センサネットワークのゲートウェイやM2Mなどインターネットへ直接つながるIoTデバイスだと演算能力を高めて、ある程度データ解析する能力が必要になっている。これをエッジコンピューティングと呼ぶが、この場合はDRAMをプロセッサと近づけるなどの工夫は必要。この用途ではDRAMは必要だが、改めて省電力というまでもない。今や、スーパーコンピュータを含めてサーバーからパソコンに至るまで低消費電力は共通の性能指標だからである。
22日の日経のニュースを読んで、あまりにも訳のわからない記事だけに問い合わせしたい気持ちを押さえて、24日の記者会見をじっと待った。ところが23日(火)になり、坂本さんから「記者会見中止のお知らせ」というメールが来た。受け取ったのは23日10:54だった。
その理由は次のように書いてあった。「この度の新プロジェクト発足に際し、世界中にありとあらゆる情報・憶測が飛び交っており、現在対応におわれております。よって、明日24日(水)に予定していました記者会見を止む無く中止させていただくことにいたしました」。不明な憶測が飛び交ったのは、日経の記事が出たためである。これは日経が勇み足をしたためだと言われても仕方がないだろう。なぜ、会見まで待てなかったのか。また、サイノキングテクノロジーもなぜ対応してしまったのか。日経はメジャー紙だけに驕り高ぶるようになったのか。あるいはサイノキングはメディア対応を甘く見ていたのか。
インテルやアップル、グーグルなどメジャーな企業では日時が決まった会見前に記事が出ることはありえない。メディア側も会見やイベント前に取材はしないという暗黙のルールを守る。今回の「事件」のためにこの新メモリ会社は設立早々ケチがついたといえるかもしれない。
(2016/03/06)
MWC報道の大いなる不満
(2016年2月23日 23:40)2月22日からスペインのバルセロナでMWC(Mobile World Congress)が始まった。しかし、新聞やネットから出てくる情報は、つまらないスマホの話ばかり。これまで何度かMWCには参加したことから考えてみると、MWCのモバイルビジネスの正確な姿が伝わってこない。開催前は、今回の目玉は、第5世代のモバイル通信、すなわち5Gだと言われていたが、実際はどうだったのか。

日本のメディアの情報はスマホの記事しか載せていない。実際に参加してみると、本来の通信オペレータに加え、クルマメーカーあり、半導体メーカーあり、部品・材料メーカーあり、クラウドサービスベンダーあり、そして通信機器メーカーがある。通信機器メーカーの中でもエリクソンやノキアネットワークス、華為技術などが5Gをはじめ様々な通信技術を見せてきた。スマホの展示は人目をひくがメジャーではない。
それでもほとんどの日本のメディアはスマホやタブレット、ガラケー等の話ばかりを報道していた。主催者は、グーグルやfacebook、AppleなどのOTT(Over-the-top)の脅威に対するオペレータはどう対応していくべきか、といった内容を真剣に議論するとか、TD-LTEとFD-LTEの対応や、モバイルの企業内での使用によるBYOD(Bring your own device)の問題などの議論や、モバイルからクラウドへのセキュリティ問題も活発であった。
今年は日本に留まっているため、残念ながら世界の動きをじかに見ることはできない。それでも海外情報を見ていると、日本のメディアの報道とは全く違う内容が多い。IoTの標準規格を決めるためにMicrosoftと、Intel、Cisco、Electrolux、GE、Qualcomm、Samsung、ARRIS、CableLabsがOCF(Open Connectivity
Foundation)を設立したというニュースが載っている。
インターネットとつながるIoTがらみでは、NB(狭帯域)-IoTのパネルディスカッションがあったことを米国の通信メディアが報じている。低消費電力で低価格のIoTはデータレートが少ないながら、大量に使われる応用に向いたセンサデバイスとなる。LTEを使っても遅いデータレートで十分なセンサノードなどの用途ではNB-IoTが向く。
また、FacebookのCEOである、マーク・ザッカーバーグ氏がサムスンの記者発表の場に登場して、これからはVR(バーチャルリアリティ)がソーシャルのプラットフォームになる、と述べたことも報じられている。サムスンのVRヘッドセットを説明しただけではなく、Facebookも何らかのVRを使って、異次元のエクスペリエンスに進出してくるようだ。
面白い用途では、インテルがAT&TのLTE通信を使ってドローンのような無人飛行機(UAV)に利用しようという提案を行っている。LTEだと通信範囲が広いためドローンの用途が大きく広がる可能性がある。両者は共同で、UAV向けのLTEの仕様を決めテストするためにコラボするという。インテルのLTEモデム(かつてインフィニオンから買収した部門)とAT&TのLTEネットワークを擦り合わせて、UAVからビデオストリーミングを見せるというデモを行ったという。LTEネットワークにドローンをつないだ時の問題点を引き出し、安全面やセキュリティ上の問題、リアルタイム通信の可能性、有人飛行機からの干渉など将来のドローンをLTEネットワークで飛ばすための検討が始まったといえる。
以上、本日ちら見しただけでもスマホ以外のトピックスが山のようにある。しかし、日経新聞をはじめメディアは、どうでもよい日本企業のスマホを相変わらず紹介しているだけだ。このままでは世界からますます遅れ、遠ざかってしまう。せめてインテルやクアルコム、エリクソンなど有名どころのCEOの基調講演くらいは聴いて報道してほしい。日本のスマホを報じても日本の業界人にとって価値ある情報なのか、もっと真剣に考えてほしい。
(2016/02/23)




